SNS採用のメリット・デメリットとは?成功事例もあわせて解説
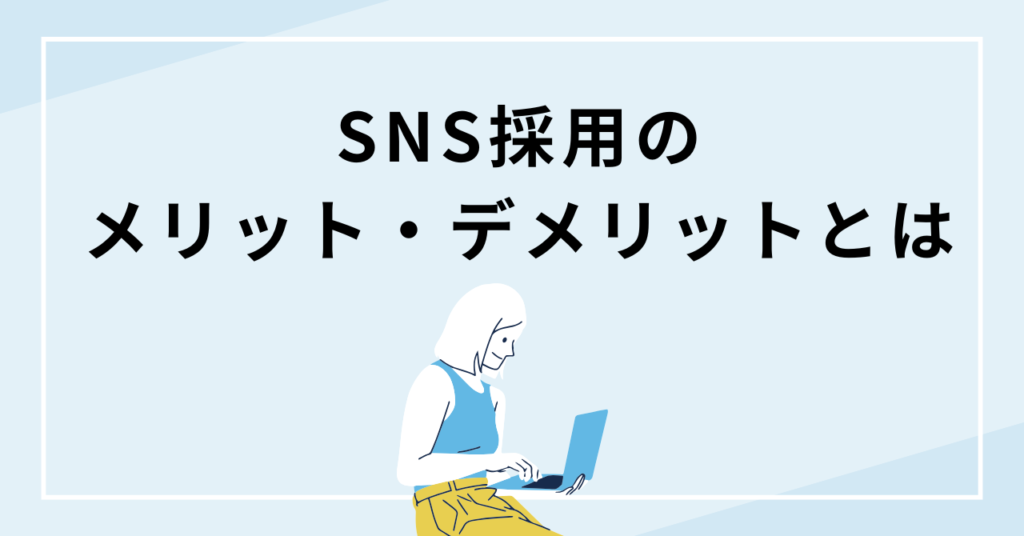
SNS採用(ソーシャルリクルーティング)は、今や多くの企業が注目する採用手法です。低コストで幅広い層にアプローチできる一方、運用にはリソースやリスクも伴います。
本記事では、SNS採用のメリットとデメリットを整理し、導入前に知っておくべき重要ポイントをわかりやすく解説。
さらに、実際の成功事例も紹介しながら、自社にとって最適な手法かどうかを判断するヒントをお届けします。
SNS採用(ソーシャルリクルーティング)とは
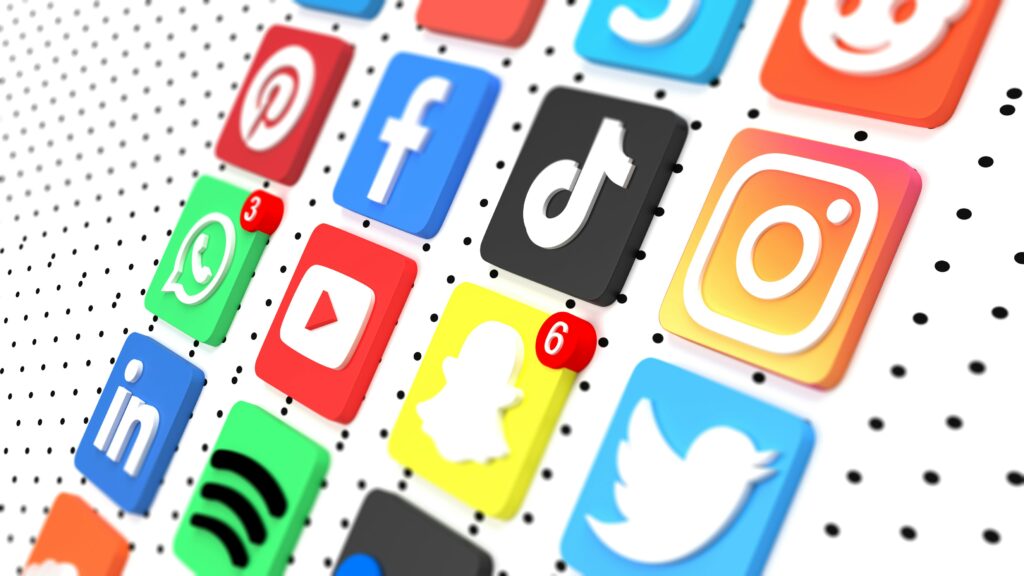
SNS採用とは、Facebook・X(旧Twitter)・Instagram・LinkedIn などのソーシャルメディアを活用した採用活動のことです。
単なる求人情報の掲載にとどまらず、
- 企業文化や社風の発信
- 求職者との直接コミュニケーション
を通じて、求職者に「ここで働きたい」と思わせる関係性を築くことを目的としています。
従来の採用手法との違い
従来の採用は、求人媒体や人材紹介会社など第三者を介した受動的なアプローチが中心で、ターゲットは転職を強く意識する「顕在層」に限られていました。
一方、SNS採用では企業が主体的に発信し、潜在層へのアプローチも可能。日常的な投稿を通じて企業の雰囲気や働く人の姿を伝えることで、応募前から共感を得られます。
また、従来の媒体は掲載期間や文字数に制約がありますが、SNSは自由度が高く、画像や動画を使ったビジュアル訴求も簡単に実現できます。
SNS採用が注目される背景
SNS採用が急速に広がっている背景には、求職者の行動変化があります。
- Z世代の約半数がSNSで企業研究をしているというデータがあり、採用広報におけるSNS活用は必須になりつつあります。
- 採用難の時代において、新たな母集団形成の手段としても期待されています。
- コロナ禍をきっかけにオンラインでの情報収集が定着し、会社説明会や面接のデジタル化が進んだことも追い風となりました。
こうした流れの中で、SNS採用は「コストを抑えながら幅広い候補者にアプローチできる手法」として企業からの注目度が高まっています。
主要SNSプラットフォームの特徴
X(旧Twitter)は、リアルタイム性と拡散力が特徴です。短文投稿が中心で、最新情報の発信に適しています。20代の利用率が高く、カジュアルなコミュニケーションが可能です。
Instagramは、ビジュアル重視のプラットフォームです。写真や動画で職場の雰囲気を伝えやすく、20〜30代の女性ユーザーが多い傾向があります。ストーリーズ機能で気軽な情報発信もできます。
LinkedInは、ビジネス特化型のSNSです。専門職やハイクラス人材の採用に適しており、プロフェッショナルな情報交換が行えます。FacebookやTikTokも、それぞれ異なる特徴を持つため、ターゲットに応じた使い分けが重要です。
SNS採用の5つのメリット

SNS採用には、従来の採用手法にはない多くのメリットがあります。ここでは、特に重要な5つのメリットについて詳しく解説します。
採用コストの大幅な削減
SNS採用の最も大きなメリットの一つは、採用コストを大幅に抑えられる点です。多くのSNSプラットフォームは無料でアカウントを作成・運用できるため、初期投資がほとんど不要です。
従来の求人広告では、1回の掲載に数十万円がかかることも珍しくありません。しかしSNSであれば0円からスタート可能。有料広告を活用する場合でも、予算に応じて出稿量や期間を柔軟に調整できるため、中小企業でも取り組みやすい仕組みです。
さらに、人材紹介会社を利用した場合に発生する成功報酬(年収の30〜35%)もSNS採用には不要です。直接採用に結びつけられるため、広告費と紹介手数料の両方を削減でき、結果的に採用ROIを高めることができます。
潜在層へのアプローチが可能
求人サイトの利用者は、すでに転職を検討している「顕在層」が中心です。しかし、優秀な人材の多くは転職を積極的に考えていない「潜在層」に含まれています。
SNSでは、日常的な情報発信を通じて潜在層へもリーチ可能です。例えば、興味深い投稿がきっかけで企業に関心を持ち、将来的な転職先候補として意識されるケースも少なくありません。
また、SNSの特性であるシェアやリツイートによる拡散力により、想定以上に情報が広がり、自社を知らなかった人材にまでリーチできます。その結果、これまで接点のなかった優秀な人材との新しい出会いが生まれる可能性が高まります。
企業の魅力をリアルタイムで発信
求人票では伝えきれない企業の魅力を、SNSなら自由に発信できます。社員の働く様子、社内イベント、日常の風景など、リアルな情報を写真や動画で伝えることが可能です。
例えば、朝礼の様子を撮影して投稿すれば、社内の雰囲気が伝わります。新商品開発の裏側を紹介すれば、仕事のやりがいを感じてもらえるでしょう。このような生の情報は、求職者の企業理解を深め、志望度を高める効果があります。
タイムリーな情報発信により、企業の「今」を伝えられるのもSNSの強み。常に新鮮な情報を提供することで、求職者の関心を維持し続けることができます。
双方向コミュニケーションで関係構築
SNS最大の特徴は、求職者と直接つながれる双方向性です。コメントやDMを通じたやり取りにより、応募前から関係性を築くことができます。
投稿に対してリアクションを返したり、質問に即座に答えたりすることで企業への親近感が高まり、「応募してみたい」という動機形成につながります。
さらに、求職者の反応を観察しながら投稿内容を改善できるため、リアルタイムで採用広報の精度を高められる点も強みです。
採用ブランディングの強化
継続的なSNS発信は、採用ブランディングの強化にも直結します。統一感のある情報発信を続けることで「この会社は透明性がある」「働きやすそう」という印象が醸成され、長期的には「働きたい会社」として認識されやすくなります。
特にZ世代を中心とした若年層は、企業がSNSでどのような発信をしているかを重視する傾向があります。親しみやすく誠実な発信を心がけることで、自然と信頼感を高めることが可能です。
結果として、強い採用ブランドは応募者数の増加だけでなく応募者の質向上にもつながります。「あの会社で働きたい」と思われる存在になれば、採用活動全体の効率も大幅に改善されます。
SNS採用の5つのデメリット

SNS採用には多くのメリットがある一方で、注意すべきデメリットも存在します。導入前にリスクや課題を理解し、適切な体制を整えてから運用を始めることが成功の鍵となります。
継続的な運用負担が大きい
SNS採用の最大の課題は、継続的な運用が不可欠である点です。アカウントを開設しただけでは効果は出ず、定期的な投稿、コメントへの対応、フォロワーとの交流といった日々の運用業務が求められます。
週に3〜5回の投稿が推奨されますが、その裏には「投稿ネタの企画」「文章作成」「写真・動画撮影」「画像編集」など多くの作業が存在します。専任の担当者がいない企業では通常業務と並行して運用する必要があり、人手不足の中小企業にとっては大きな負担となりがちです。
さらに、SNS採用は成果が出るまでに時間がかかるため、運用担当者のモチベーションを維持するのも課題です。結果が見えないまま更新を止めてしまうと、積み重ねた努力が水の泡になるリスクもあります。
炎上リスクとブランド毀損の可能性
SNSは拡散力が高い分、炎上リスクを常に抱えています。不適切な発言や誤った対応が拡散されれば、数時間で企業全体の信用を大きく失うこともあります。
過去には、社員の不用意な投稿や不適切な表現が波紋を呼び、企業の評判を大きく損なった事例もありました。採用目的で始めたSNSが逆に企業ブランドを傷つける原因となるのは本末転倒です。
炎上を防ぐには、投稿前のダブルチェック体制や社内向けのSNSガイドラインが必須です。また、万一炎上が発生した場合に備えて、対応フローや広報部門との連携ルールを整備しておく必要があり、リスク管理に相応の労力がかかる点は無視できません。
即効性がなく成果まで時間がかかる
SNS採用は、短期間で成果が出る手法ではありません。フォロワーを獲得し、エンゲージメントを高め、信頼関係を築いて応募につなげるには、数カ月から1年程度の継続的な取り組みが必要です。
そのため、「今すぐ人材が欲しい」という採用ニーズには対応しづらく、急募ポジションの場合は求人媒体や人材紹介との併用が不可欠です。
また、経営層が短期的な成果を求める場合には導入の理解を得にくいこともあります。SNS採用は長期的な投資効果を重視する施策であるため、KPI設計やROIを可視化して説明できる体制づくりが欠かせません。
運用スキルと知識が必要
効果的なSNS運用には、文章力・デザイン力・動画編集スキル・マーケティング知識など多岐にわたるスキルが求められます。
- 魅力的な文章の作成
- 写真・動画の撮影や編集
- 適切なハッシュタグの選定
- プラットフォームごとのアルゴリズム理解
これらをすべて兼ね備えた人材は限られており、社内で育成するには時間がかかります。外部委託すればスキル不足は補えますが、その分コストが発生します。
つまり「無料で始められる」というSNS採用の魅力も、実際には人的リソースという見えにくいコストを考慮する必要があるのです。
プライバシー管理の難しさ
SNS採用では、社員や職場の様子を発信する場面が増えるため、プライバシー管理の課題が避けられません。
- 顔出しをするかしないか
- 実名を公開するか匿名にするか
- 退職者のコンテンツをどう扱うか
こうした判断には常にリスクが伴います。顔出しや実名を強制することはできませんが、匿名性が高すぎると親近感が伝わらず効果が薄れる可能性があります。また、退職後に残された投稿がトラブルを生むケースもあります。
SNS採用の成功事例に見る効果的な運用方法

SNS採用は、業界や企業規模を問わず成果を出すことが可能です。ここでは、製造業・スポーツ業界・歯科業界での具体的な成功事例を紹介し、それぞれの取り組みから学べる運用方法と成果を出すためのポイントを解説します。
【製造業】SKB様のX(旧Twitter)採用成功事例
金物メーカーのSKB様は、BtoB業界でありながらゼロからX運用を始め、大きな成果をあげた事例です。「製造業でもSNS採用は成果を出せる」ということを証明しました。
0から始めて半年で問い合わせ2件を獲得
SKB様はフォロワー0人からスタートし、半年で2,271人のフォロワーを獲得。さらにX経由で新規問い合わせ2件を獲得し、月間売上約100万円の増加という実績を生み出しました。
成功の鍵は、親しみやすさを前面に出した運用です。月間約40ツイートを投稿し、必ず複数のハッシュタグを活用。専門的な情報だけでなく日常的な話題も発信することで、堅い印象を持たれがちなBtoB企業のイメージを刷新しました。
また、固定ツイートに自己紹介投稿を設定し、初めて訪れたユーザーにも企業概要がすぐ伝わる工夫を実施。フォロワー獲得から信頼構築までの導線を最適化しました。
BtoB企業でも実現できるSNS採用戦略
BtoB企業こそSNSを通じた差別化が有効です。SKB様は積極的にDM送信を行い、ただの情報発信に留まらない「対話型アカウント」として認知されました。
コメントには必ず返信し、やり取りが続くこともしばしば。こうした丁寧なコミュニケーション姿勢がユーザーとの信頼関係を育て、結果的にエンゲージメント率を0%から7.16%へ大幅改善させました。
この事例は、「BtoB企業でも正しい戦略と双方向の姿勢があれば、SNS採用は十分に成果を出せる」ことを示しています。
【スポーツ業界】オルカ鴨川FC様のInstagram採用成功事例
女子サッカーチームのオルカ鴨川FC様は、Instagramを活用してスクール運営の問い合わせを増加させることに成功しました。
DMで問い合わせを獲得した施策
オルカ鴨川FC様の大きな成果は、InstagramのDMを通じてスクールに関する問い合わせが直接届くようになったことです。フォロワー数は3,436人から4,315人へ増加し、ファンベースの拡大にもつながりました。
投稿では、一方的な情報発信に留まらず、質問を投げかけたり試合の実況をリアルタイムで投稿したりすることでユーザーの共感を生み出しました。これにより、PDCAサイクルを高速で回し、投稿の質と成果を継続的に改善しています。
エンゲージメント率6.15%→14.62%へ改善
研修前は6.15%だったエンゲージメント率が14.62%へと、2倍以上の向上を達成。インプレッション数も3,028から22,414へと約7.4倍増を実現しました。
この数値は、X(Twitter)でフォロワー1,000〜1万人のアカウントの平均エンゲージメント率(約4%)を大きく上回る成果です。
さらに、X経由でInstagramアカウントを宣伝するクロスプラットフォーム戦略を実施し、インプレッション率が5%アップするなど、複数SNSの連携による相乗効果も確認されました。
【歯科業界】成田デンタル様のX(旧Twitter)採用成功事例
歯科技工の総合商社である成田デンタル様は、X運用を通じて驚異的な採用成果を達成した事例です。
わずか6回の研修で20名採用を実現
SNSCHOOLの研修を導入後、成田デンタル様はわずか6回の研修期間中にX経由で20名の採用に成功しました。応募者数は136人、面接数は62人と非常に高い成果を記録。
成功の要因は、複数アカウントの戦略的運用です。企業公式アカウントに加え、総務・採用・営業など部署ごとにアカウントを設け、それぞれのターゲットに合った情報を発信しました。
さらに、求人情報だけでなく、社内の日常や雰囲気が伝わる投稿を積極的に発信し、応募ハードルを下げて求職者が安心して応募できる環境を整えました。
フォロワー950人→1,484人に増加させた戦略
フォロワー数は研修前の950人から1,484人へと増加。この成長の背景には、戦略的なユーザーコミュニケーションがあります。
具体的には、採用したい層のアカウントに「1日2〜3回のいいね攻撃」を行い、その後リプライや引用RTで関係を深め、最終的にDMで商談や採用面談へとつなげました。
この一連の流れを運用開始からわずか1ヶ月で確立。SNSで築いた信頼関係が採用成功だけでなく、月間売上40万円以上の増加にも貢献しました。
SNS採用を成功させるためのコツ

SNS採用はコスト削減や潜在層へのアプローチといった大きなメリットがある一方で、継続的な運用負担や炎上リスクといったデメリットも抱えています。
では、これらの課題を踏まえた上で、どうすればSNS採用を成功に導けるのでしょうか。ここでは、実践的なポイントを3つに整理して解説します。
運用体制の構築方法
SNS採用の第一歩は、持続可能な運用体制の構築です。担当者が曖昧なままでは更新が止まり、成果は期待できません。まずは専任もしくは兼任で担当者を決め、責任の所在を明確にすることが重要です。
その上で、週単位・月単位の投稿スケジュールを作成し、ネタをあらかじめストックしておきましょう。これにより、更新が途切れるリスクを防ぐことができます。さらに、現場や各部署から情報提供を受けられる仕組みを作れば、コンテンツの幅が広がります。
加えて、投稿管理ツールの活用も有効です。予約投稿機能を使えば、複数の投稿をまとめて準備できるため、通常業務との両立がしやすくなります。小さな取り組みから始め、段階的に体制を強化していくことが現実的かつ成功への近道です。
コンテンツ戦略の立て方
SNS採用における最大の成果要因はコンテンツ戦略にあります。まずは採用したい人材像(ペルソナ)を明確にし、その層が関心を持つ情報を設計することから始めましょう。
次に、投稿する内容をカテゴリごとにバランス良く分配します。例えば、社員紹介30%、仕事内容30%、社内イベント20%、業界情報20%といった配分です。こうすることで、求職者が「この会社で働くイメージ」を自然と描けるようになります。
また、季節性やトレンドを反映させた投稿も効果的です。例えば、新卒採用期に合わせて社員インタビューを発信したり、流行のハッシュタグを活用するなど、求職者の目に留まる工夫を加えると良いでしょう。ただし、採用と直接関係のないコンテンツに偏りすぎると目的を見失うため、常に「採用につなげる」視点を持つことが重要です。
炎上対策とリスクマネジメント
SNS採用の運用で軽視できないのが炎上リスクです。拡散力が大きいSNSだからこそ、一つの不適切な投稿が企業全体のイメージを損なう恐れがあります。
まずは、SNS運用ガイドラインを策定し、投稿してよい内容・避けるべき内容を明文化しましょう。さらに、投稿前には最低2人以上で内容を確認するダブルチェック体制を導入することでリスクを低減できます。個人情報の漏洩や差別的表現がないかなど、細部まで確認が必要です。
また、危機管理マニュアルの事前準備も欠かせません。炎上の兆候を察知した際の初動対応、社内エスカレーションのフロー、公式コメントの出し方などをあらかじめ決めておくことで、トラブル発生時の被害を最小限に抑えることができます。
まとめ
SNS採用は、コスト削減や潜在層へのアプローチ、企業の魅力をリアルに伝えられるといった従来の手法にはない強みを持つ一方で、継続的な運用負担や炎上リスク、即効性の低さといった課題も存在します。
しかし、運用体制の構築・明確なコンテンツ戦略・徹底したリスク管理という3つのポイントを押さえれば、これらの課題は乗り越えられます。持続的かつ戦略的に取り組むことで、SNS採用は確実に成果へとつながるでしょう。
SNS採用を自社で成功させたい方へ
SNS採用は、中小企業にとっても非常に有効な手法ですが、成果を出すには戦略的な運用と継続的な改善が欠かせません。
BESWが提供する 「SNSCHOOL」 では、これまでに600社以上の支援実績をもとに、企業が自走できるSNS運用のノウハウを提供しています。
- 現場ですぐに使える実践的な研修プログラム
- ペルソナ設計・コンテンツ企画のサポート
- KPI設計から効果測定・改善提案まで一貫支援
- 社内にSNS運用担当を育成できる仕組み
「SNSを始めたいけれど成果につながらない」
「求人広告費を削減しつつ優秀な人材を採用したい」
そんな課題をお持ちの方は、ぜひ一度SNSCHOOLをご検討ください。
SNSの内製化支援を行っています
自社のSNSがなかなか伸びない…
SNSで集客したいけど何から始めたらいいかわからない
そんな企業様でも0から始めて集客を成功させています。
こちらから成功事例を集めた資料を無料でダウンロードいただけます。
